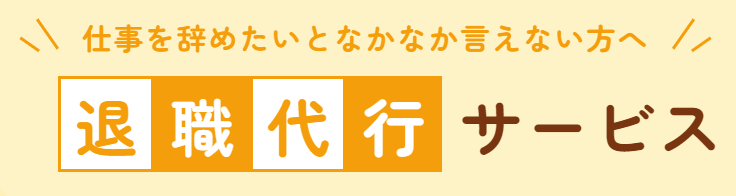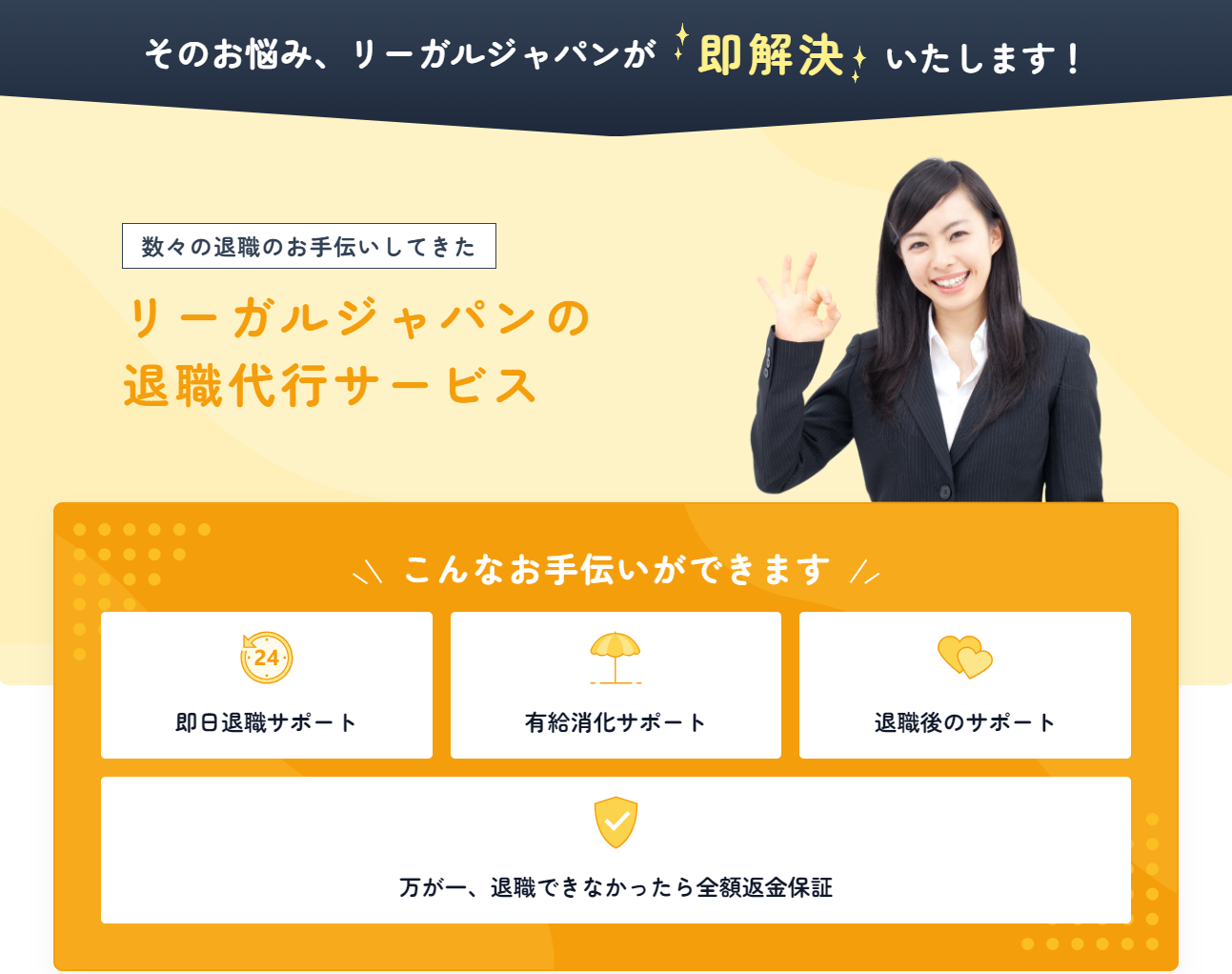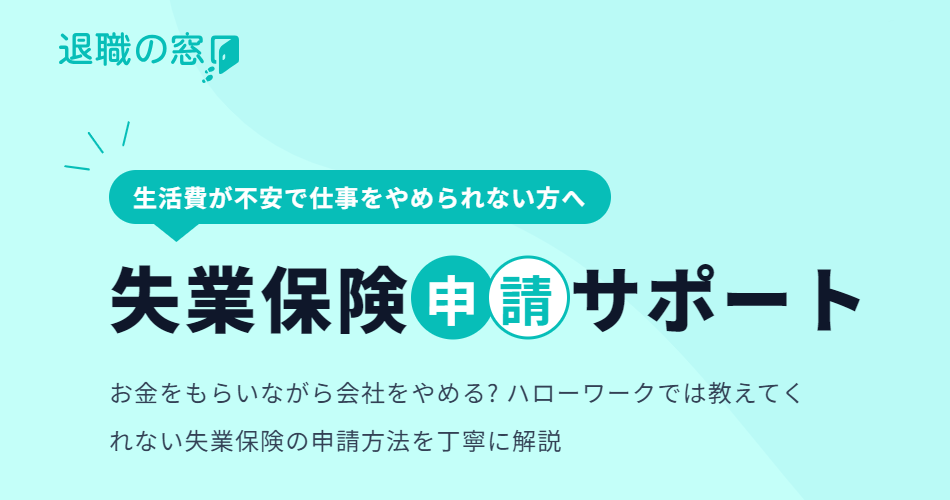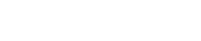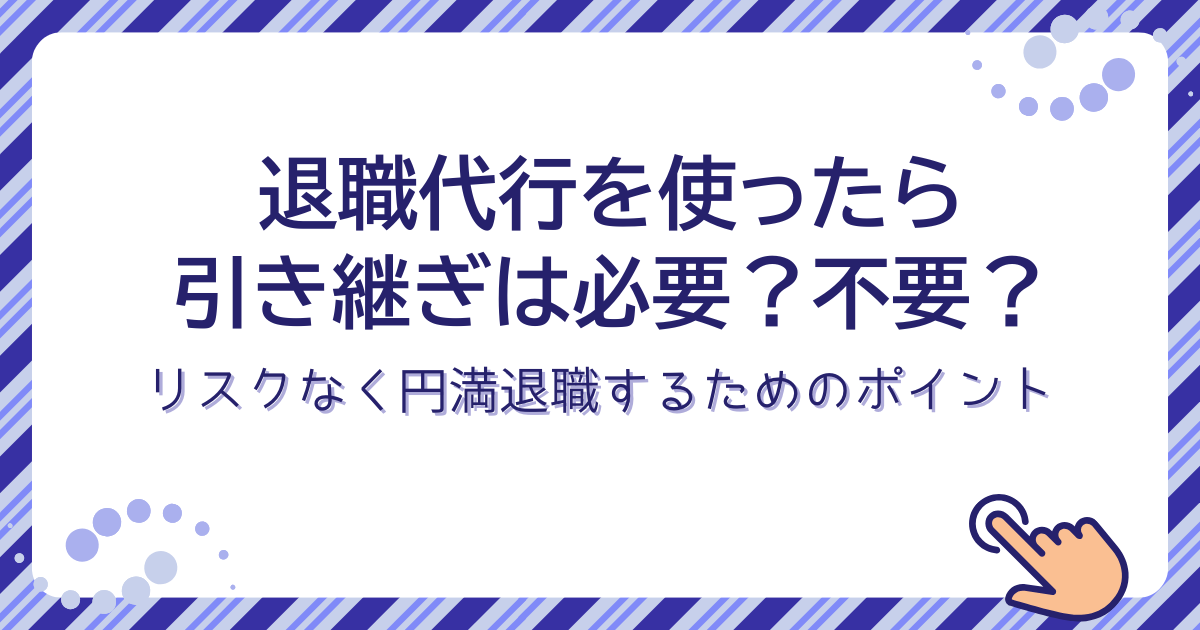退職代行サービスを利用して職場を辞めるとき、どのように引き継ぐべきか、そもそも引き継ぎは必要なのかという悩みを抱える方は少なくありません。
退職代行サービスを利用する場合でも業務の引き継ぎは基本的に必要で、適切に対応することが円満退職への鍵です。
法律上の明確な義務規定はありませんが、引き継ぎを怠ると損害賠償請求をはじめとする、トラブルのリスクが発生するため注意が必要です。
もし退職する際に引き継ぎが負担と感じるなら、出社せずに引き継ぎできる方法を活用しましょう。
この記事では、退職代行サービス利用時の業務引き継ぎの義務やトラブルを避ける方法について詳しく解説します。
退職代行を使えば引き継ぎ不要で辞めることはできる
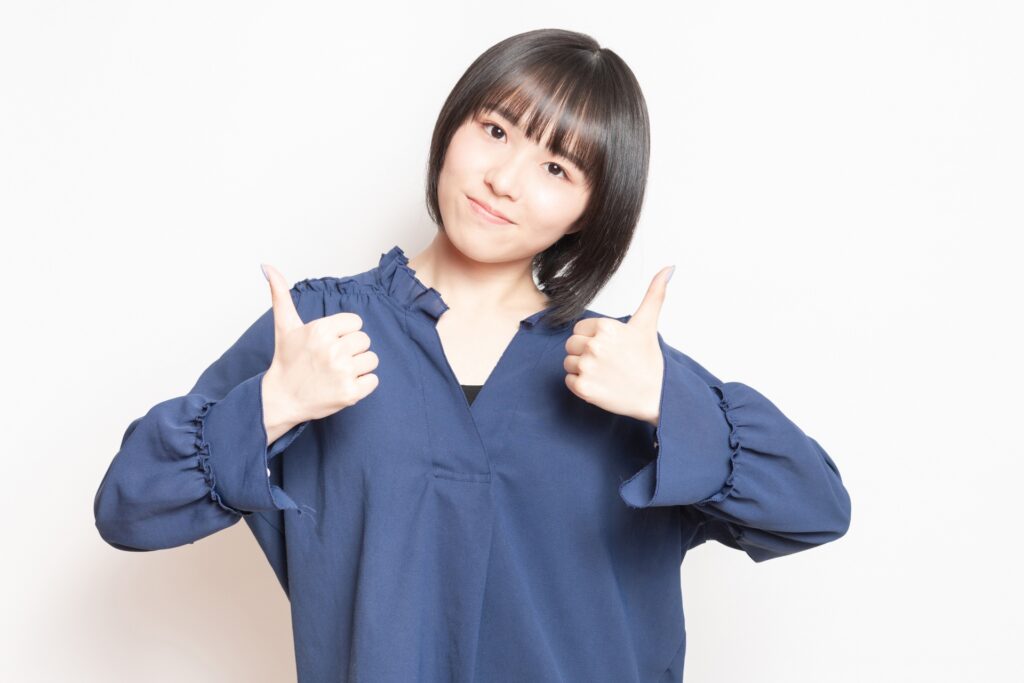
退職代行を使えば、引き継ぎ不要で辞めること自体は可能です。
退職は民法で保障された権利であり、民法の規定には職務の引き継ぎについて法的な義務があるとは明記されていません。
ただし、退職代行を利用したすべてのケースで引き継ぎが不要とは限らないため注意が必要です。
それでは、退職代行と引き継ぎに関連する内容について解説します。
法律には引き継ぎの義務に関する規定がない
法律には引き継ぎに関する規定がなく、必ずしも引き継ぎが必要だとは言い切れません。
民法では雇用者と被雇用者の契約関係についていくつもの条文が定められていますが、引き継ぎに関する条文はありません。
ただし、民法第1条2項には、権利の行使は信義誠実に行わなければならないと定められています。
(基本原則)第一条 2権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
引用:e-Gov 民法
引き継ぎをしないことで雇用者に損害を与える可能性がある場合は、信義誠実の原則に従い、引き継ぎが必要と判断されることがあります。
つまり、退職代行を利用しても、利用者の状況によっては引き継ぎが必要になる場合があるわけです。
退職は民法で保障された権利
退職は民法で保障された権利であり、雇用者であってもその権利の行使を妨げてはなりません。
民法には、退職について次のような条文があります。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第六百二十七条当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:e-Gov 民法
原則として、被雇用者は退職日の2週間前に雇用契約の解約を申し入れれば退職が可能です。
会社から「退職は認めない」「この日までは働いてもらう」と言われたとしても、民法の規定に従って解約を申し入れれば退職することができます。
ただしトラブルになる恐れはある
法的に引き継ぎの義務はなく、退職は保障された権利ですが、自己判断で行動すると雇用者とトラブルになる恐れがあります。
たとえば、引き継ぎしないことで会社の業務に支障が生じた場合、顧客に伝えるべき内容が後任に伝わっていない場合などです。
会社に損害を与えた場合、損害賠償を請求されたり、元同僚との関係が悪化したりする可能性があります。
引き継ぎをしなかった方として情報が共有されているケースもあり、同業他社に転職する際に不利になる場合もあるため注意が必要です。
退職代行を使っても引き継ぎをした方がいいケース

トラブルになる恐れはあるものの、退職代行を使えば引ぎ継ぎなしでやめることは可能です。
しかし、中には、退職代行を使ったとしても引き継ぎをするべきケースがあります。具体的には次のとおりです。
- 就業規則に引き継ぎの義務が明記されている
- 会社の機密を多数抱えている
- 重要な取引先を抱えている
自身の状況が上記に当てはまる場合は、これから説明する内容をしっかりとチェックしてください。
就業規則に引き継ぎの義務が明記されている
就業規則に引き継ぎの義務が明記されている会社に勤めている場合、退職代行を利用する場合でも引き継ぎが必要です。
雇用者と被雇用者は雇用契約を締結しており、就業規則を守らない場合、会社から契約違反を問われる可能性があります。
損害賠償請求について裁判所に民事訴訟を起こされた場合、賠償の有無や金額は総合的に判断されます。
総合的に判断する際に就業規則のルールを守らなかったことが、訴訟内容に影響を与えるかもしれないことを認識しておきましょう。
会社の機密を多数抱えている
会社の機密を多く扱っている方は、退職代行を利用する際には引き継ぎをした方がよいでしょう。
機密事項が漏洩すると業績に一時的な悪影響を及ぼすのみならず、評判の低下によって会社の経営が傾く事態にもなりかねません。
多くの機密を扱っている方は、会社に悪影響を与えないためにも、引き継ぎをして情報や資料を漏れなく提供する必要があります。
システムのアクセス権限やパスワードも機密事項に該当するため、退職前に情報を整理して引き継ぎをおこないましょう。
重要な取引先を抱えている
重要な取引先との結びつきが強い仕事をしている方は、退職代行を利用する場合でも引き継ぎをした方がよいでしょう。
取引先との関係は、担当者によって維持されています。
担当者が退職した際、前任者と後任者の間に能力の差がある場合、取引先との関係が悪化する可能性があります。
しかし、必要な情報を後任者と共有すれば、能力の差を補うことができるため、引き継ぎは取引先との関係を維持するうえで重要です。
引き継ぎをしないことで取引先との関係が悪化した場合、損害賠償を請求されるリスクが高まるため注意が必要です。
引き継ぎなしで退職するリスク

退職代行サービスを利用して引き継ぎせずに退職することは可能ですが、さまざまなリスクや問題が発生する可能性があります。
法律には明確な引き継ぎ義務の規定はありませんが、民法における信義誠実の原則や就業規則に基づき、引き継ぎが求められるケースがあります。
適切な引き継ぎを行わないと、損害賠償請求や退職後のトラブル、人間関係の悪化などの重大なリスクが生じるでしょう。
会社から損害賠償請求される恐れ
引き継ぎせずに退職し、会社に具体的な損害が発生した場合、損害賠償を請求される可能性があります。
とくに自身が担当していた顧客情報や、重要プロジェクトの情報を引き継がなかったことで会社が損失を被った場合は、賠償請求のリスクが高まります。
過去の事例では、引き継ぎ不足による損害に対して480万円の支払い命令が出されたケースもあるため、注意が必要です。
以上によれば,被控訴人の債務不履行による損害額は,480万円の限度 でこれを認めるのが相当である。
引用:知的財産高等裁判所 競業行為差止等(東京地方裁判所 平成27(ワ)16719)
東京裁判所は引き継ぎしないことで損害を与えた場合、会社には損害賠償を請求する権利があるとしました。
引き継ぎせずに退職することは可能ですが、一方で損害賠償請求されるリスクがある点については理解しておかなければなりません。
退職後に連絡が来る恐れ
引き継ぎを十分に行わずに退職すると、退職後も会社から業務に関する問い合わせや出社要請が続くことがあります。
民間業者による退職代行サービスの場合は、会社と本人の間で協議や交渉は行えないよう法律で定められているため、対応が困難です。
しかし、労働組合や弁護士事務所が運営する代行サービスを利用すれば、退職後のトラブルに対応してくれます。
労働組合や弁護士事務所が運営する退職代行サービスは、会社と交渉する権利があり、依頼者に不利となる行動をしないよう要請できます。
退職後も安心して次のステップに移りたい方には、民間業者以外が運営する退職代行サービスがおすすめです。
同僚や取引先との間で関係が悪化する危険性
引き継ぎを行わずに退職すると、残された同僚の業務負担が急増するため、人間関係が悪化する可能性があります。
同僚たちは突然増えた仕事に対応しなければならず、その不満が退職者に向けられることは少なくありません。
また、取引先との関係においても問題が生じる可能性があります。担当者が突然連絡が取れなくなることで、取引先は次のような不安を感じるでしょう。
- 業界内での評判の低下
- 将来的な転職活動への悪影響
- 職業的なネットワークの喪失
とくに同じ業界で再就職を考えている場合は、引き継ぎをきちんとおこなって円満に退職することが重要です。
懲戒解雇の扱いになる恐れ
引き継ぎをせずに退職すると、会社から懲戒解雇として扱われる恐れがあります。
懲戒解雇とは、従業員が重大な規律違反や非行をおこなった際に、会社が科す懲戒処分のことです。
引き継ぎをせずに退職した場合でも、一般的には懲戒解雇に該当するほどの行為とはみなされません。
しかし、退職時に会社に損害を与えた場合、経営陣の判断によっては感情的になり、懲戒解雇として扱われる可能性もあります。
不当な取り扱いは裁判で覆る可能性もありますが、裁判には時間や費用がかかるため、できる限り避けたい事態と言えるでしょう。
退職証明書に不利な事実を記載される恐れ
引き継ぎをしなかった場合、退職証明書に不利な事実が記載される可能性があります。
退職証明書とは、退職した事実を証明する書類です。国民健康保険や国民年金への加入手続きのほか、転職先の会社から提出を求められます。
退職証明書には勤務期間や賃金、退職理由などが記載されています。
退職した会社との関係が悪化している場合、事実を誇張した内容で退職理由が記載されるかもしれません。
記載内容を訂正してもらうには費用や時間がかかるため、不正な記載を防ぐためにも、事前に引き継ぎをすることが大切です。
出社なしで引き継ぎしたい方におすすめの方法
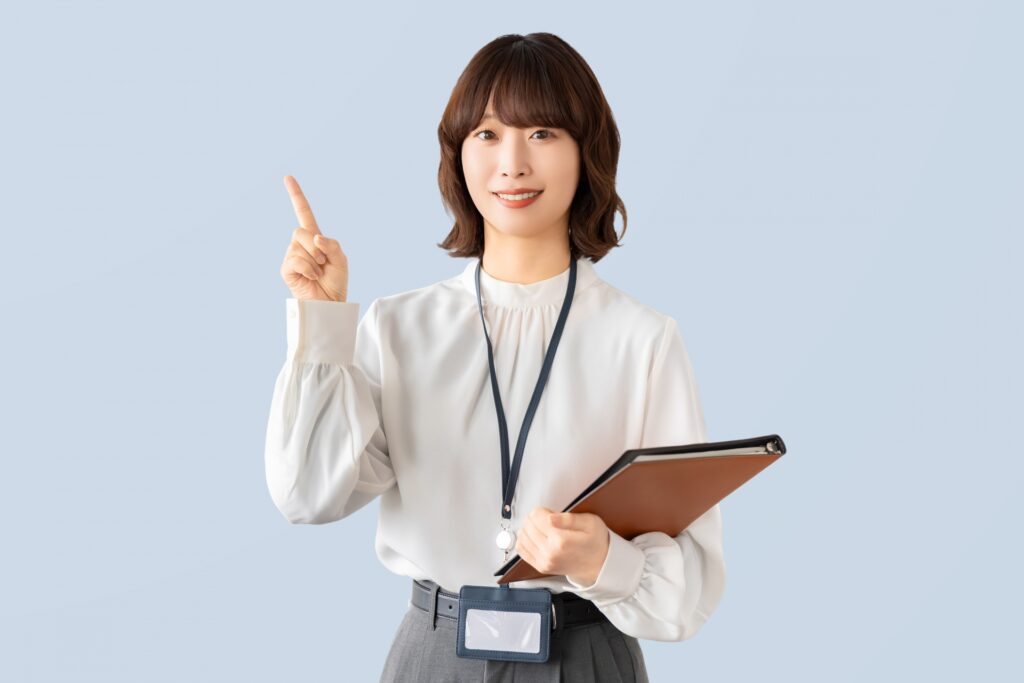
退職代行を利用する際に引き継ぎをすると決めた場合でも、出社したくない方は多いでしょう。
出社せずに引き継ぎができる方法はいくつかあり、それらの方法を理解していれば、会社に出向かずに済みます。
出社したくない方は、これから紹介する方法を実践してみてください。
引き継ぎ書類を作成する
退職代行を利用する際に、引き継ぎ書類を作成すれば直接連絡の時間を削減できます。
引き継ぎ書類は退職代行を利用する際の最も基本的かつ重要なツールです。
出社せずとも作成・提出可能なため、パワハラなどの理由で職場に行けない状況でも対応できます。
詳細で体系的な引き継ぎ書類は、会社側からの追加要求を減らす効果もあるため、事前に作成しましょう。
引き継ぎ書類には以下の情報を含めることが大切です。
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 業務概要 | 担当業務の全体像と主な責任範囲 |
| 進行中の案件 | 現在取り組んでいるプロジェクトとその進捗状況 |
| 定期業務 | 日次・週次・月次でおこなうう定期的なタスクとその手順 |
| 取引先情報 | 取引先の連絡先、窓口担当者、案件履歴 |
| システム情報 | 業務で利用するシステムのログイン情報や操作方法 |
| 保管場所 | 重要書類やデータの保存場所と権限情報 |
具体的な顧客案件や数値目標についても言及すると、より実用的な引き継ぎ資料になります。
カレンダー機能がある社内ツールを利用しているなら、今後3か月分の予定業務を記載するなど、具体的な情報を盛り込みましょう。
電子メールやクラウドを活用する
電子メールやクラウドを活用すれば、話し合いで引き継ぐ必要はありません。
退職する前であれば、まだ会社で勤務していたときのインフラを利用できます。
電子メールのアドレスは残っており、クラウドのシステムも利用可能な状態です。
直接対話が必要のないツールを使用すれば、直接話し合いせずに済むだけではなく、引き継ぎ内容を体系的に会社側に伝えられます。
通知機能が付いているツールもあるため、連絡ミスの防止にもつながる可能性があります。
リモート会議で引き継ぎする
リモート会議の場が設けられれば、効率的に引き継ぎできます。
対面が嫌だと感じつつも、細かなニュアンスを伝える必要がある場合、引き継ぐには直接会話が必要になる場合があります。
リモート会議を利用すれば、表情や声のトーンを伝えられるため、文字のみで引き継ぐよりも効果的です。
会議の時間をあらかじめ設定しておけば、事前準備ができ、終了時間が明確になるため、引き継ぎの効率も高まります。
特殊なケースにおける引き継ぎ

特殊な状況での退職では、通常の引き継ぎ方法が適用できないことがあります。
パワハラ被害者の権利保護、病気休暇中の配慮、機密情報の適切な管理、そして最適な引き継ぎ期間の設定が重要です。
状況に応じた柔軟な対応と法的権利の理解が必要になるため、該当する方は詳細を把握しておきましょう。
パワハラ被害者は対面での引き継ぎを拒否できる
パワハラ被害を受けている従業員には、加害者との直接対面を拒否する権利があります。
労働安全衛生法の改正により、事業者には従業員の心身の健康を守る安全配慮義務が課されており、パワハラ被害者は対面での引き継ぎを拒否できます。
引き継ぎ拒否した場合、退職後に会社から嫌がらせを受けるケースもあります。
しかし、退職代行サービスに依頼すれば、書類未交付や懲戒解雇処分などの嫌がらせに対して対応できることもあるため安心です。
なお、精神科医の診断書があれば、引き継ぎの免除や軽減を会社側に要求することも可能です。
最高裁判例では、パワハラが原因で精神疾患を発症した場合、会社の安全配慮義務違反として損害賠償請求が認められた事例もあります。
病気による休暇中は健康に最大限配慮してもらえる
長期病気休暇中の従業員が退職する場合、会社は健康状態に配慮しなければなりません。
健康に問題がある場合は医師の診断に基づき、健康状態を最優先にした引き継ぎ計画を立てましょう。具体例は次のとおりです。
- 段階的な引き継ぎスケジュールの設定(1日2時間から始めるなど)
- デジタルツールを活用した自宅からの引き継ぎ資料作成
- 録音・録画による説明の事前準備
東京地裁の判例では、うつ病で休職中の従業員に対し、会社が無理な出社を求めたことで症状が悪化した場合、会社側の賠償責任が認められています。
病状に応じた配慮を受ける権利は法的に保護されており、退職時の引き継ぎにおいても同様です。
機密情報取扱者は引き継ぎ期間が長くなる恐れあり
機密情報取扱者は、引き継ぎ事項が多く、長い期間をかけて引き継ぎしなければなりません。
機密情報を扱う立場にある従業員の退職では、情報セキュリティと円滑な業務継続の両方を確保する慎重な引き継ぎが求められます。
具体的な期間は企業によって異なりますが、大手IT企業ではCSOなどの重要な機密情報取扱者が退職する際、専門の移行チームを編成し、3〜6ヶ月の引き継ぎ期間を設けるケースもあります。
あまりにも長引く場合は次の職場への入社に影響を及ぼす恐れもあるため、転職前から事前に引き継ぎ期間に関する情報を探っておくことをおすすめします。
引き継ぎをするときの重要なポイント

退職する際には、すべての業務を引き継ぐ時間はありません。
重要な業務を優先し、引き継ぐ内容を明確にする必要があります。
効率的に引き継ぐためのポイントを押さえ、トラブルの発生を防ぎ、退職後も会社と良好な関係を維持しましょう。
重要業務の完了を優先させる
重要業務の完了を優先させれば、効率よく引き継ぎでき、短時間で話し合いが終わります。
限られた引き継ぎ時間や労力の中では、業務の重要度に応じた優先順位付けが不可欠です。
すべての業務を同じ詳細さで引き継ぐことは現実的ではないため、会社への影響度や緊急度に基づいて重点的に引き継ぐべき業務を選別しましょう。
効果的な優先順位付けのための分類例は、次の通りです。
| 優先度 | 業務タイプ | 引き継ぎレベル |
|---|---|---|
| 最優先 | 収益に直結する顧客対応業務 | 詳細な手順と背景情報まで提供 |
| 高優先 | 締切が迫った進行中のプロジェクト | 現状と今後必要なアクションを明示 |
| 中優先 | 定期的に発生する業務 | 基本的な手順と注意点を記載 |
| 低優先 | 他部署と重複する業務や簡易な作業 | 概要レベルの説明で十分 |
とくに締め切りが迫っている案件や、大口顧客に関わる業務は最優先で詳細な引き継ぎをおこなうことで、会社への影響を最小限に抑えられます。
引き継ぎ期間を十分に確保する
引き継ぎ期間を十分に確保すれば、伝達不足を防止でき、会社側とのトラブルを防止できます。
引き継ぎ期間は業務の複雑さや重要度によって調整すべきで、民法上の2週間にこだわる必要はありません。
適切な期間設定は、円満な退職と円滑な業務移行の両立に不可欠です。
| 職種 | 推奨期間 | 考慮すべき要素 |
|---|---|---|
| 一般事務職 | 2週間~1か月 | 業務の標準化度、文書化レベル |
| 営業職 | 1~2か月 | 顧客関係の深さ、案件の進行状況 |
| 専門技術職 | 1~3か月 | 専門知識の複雑さ、代替人材の有無 |
| 管理職 | 2~6か月 | 組織への影響度、戦略的判断の重要性 |
引き継ぎ期間の交渉では、退職者と会社双方の利益バランスを考慮します。
退職の申し出と同時に引き継ぎ期間についても話し合うことで、双方が納得のいく形で進めやすくなるため、事前に話し合う内容を用意してみてください。
引き継ぎの内容を上司と十分に相談する
引き継ぐ内容について上司と十分に相談しておけば、必要な情報を整理できます。
情報には重要度があるため、何を優先すべきか決める必要がありますが、自身で判断するのは難しいものです。
不要な情報ばかり引き継いでしまうと、会社に迷惑をかけてしまうかもしれません。
しかし、上司に引き継ぐべき情報を確認しておけば、必要な情報を効率よく会社と共有できます。
引き継ぎの内容は明確にする
引き継ぎの内容を明確にすることで、情報を共有しやすくなり、スムーズに情報を共有できるようになります。
どのような情報を引き継ぐのかを明確にしておくと、受け取る側も事前に何を確認すればよいか把握できます。
共有する情報を明確にすれば、退職者も後任者も打ち合わせの進め方を理解しやすくなり、引き継ぎにかかる時間の短縮が可能です。
提供する内容を事前に書類にまとめたり、退職前に取り組んでいたプロジェクトの内容をあらかじめ報告したりしておくなど、明確にする方法はいくつもあります。
退職代行サービスならトリケシがおすすめの理由
退職代行サービスなら「トリケシ」がおすすめです。
トリケシをおすすめする理由は、次の3つです。
- 労働組合運営のため民間より対応範囲が広い
- 24時間LINE相談対応!即日退職もOK!
- 退職後のアフターフォローも充実
退職代行サービスといっても、会社ごとにサービス内容は異なります。
サービス内容が充実している退職代行サービスを選べば、スムーズに退職できるでしょう。
労働組合運営のため民間より対応範囲が広い
トリケシは労働組合である日本労働産業ユニオンが運営しており、民間企業よりも対応できる範囲が広いという特徴があります。
労働組合は「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体です。
引用:厚生労働省 労働組合
労働組合は労働条件の改善を図る専門的な組織であり、団体交渉権を行使できます。
団体交渉権を行使して労働組合が会社と直接交渉するため、退職者が会社と交渉する必要はありません。
たとえば、有給消化後の退職や退職日の調整などの交渉は、トリケシが代わりにおこないます。
交渉のプロに任せることで、希望する条件で退職しやすくなります。
24時間LINE相談対応!即日退職もOK!
トリケシでは24時間、LINEで相談を受け付けており、場合によっては即日退職できるケースもあります。
24時間、利用者からの相談を受け付けているため、早めに相談すれば、その日のうちに退職することも可能です。
また、LINEを通じて相談から退職代行の申し込みまででき、必要書類もすべて郵送で完結します。
トリケシなら、対面や電話で自身の意思を伝えることが苦手な方でも、簡単かつ安心して退職代行サービスを利用できます。
退職後のアフターフォローも充実
トリケシは、退職後のアフターフォローも充実しています。
退職後は、辞めた会社から離職票や雇用保険被保険者証を受け取る必要がありますが、まれにすぐに受け取れない場合もあります。
しかし、トリケシでは各種書類の受け取りまでサポートするため、退職後の不安も解消できます。
また、再就職先が決まっていない場合でも、無料の転職サポートを受けられるため安心です。
退職のみではなく、将来のことまで考えたい方には、トリケシの退職代行サービスが適しています。
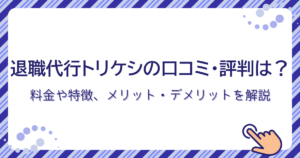
まとめ

退職代行サービスを利用する場合でも、業務の引き継ぎは基本的に必要です。
法律上の明確な義務規定はないものの、引き継ぎを怠ると損害賠償請求などのトラブルリスクが生じる可能性があります。
引き継ぎの負担を減らしたい場合は、弁護士事務所や労働組合が運営する退職代行サービスを使うことも方法のひとつです。
労働組合が運営する退職代行サービスの「トリケシ」は、基本的に即日退職できるよう会社と交渉します。
交渉に成功すれば引き継ぎの必要はありませんし、仮に引き継ぎが必要だったとしても出社以外の方法を提案します。
引き継ぎの負担を軽くしたいとお考えの方は「トリケシ公式サイト」から、お気軽にご相談ください。