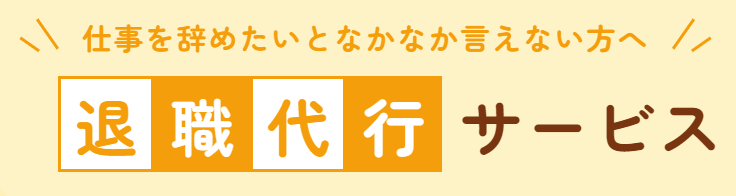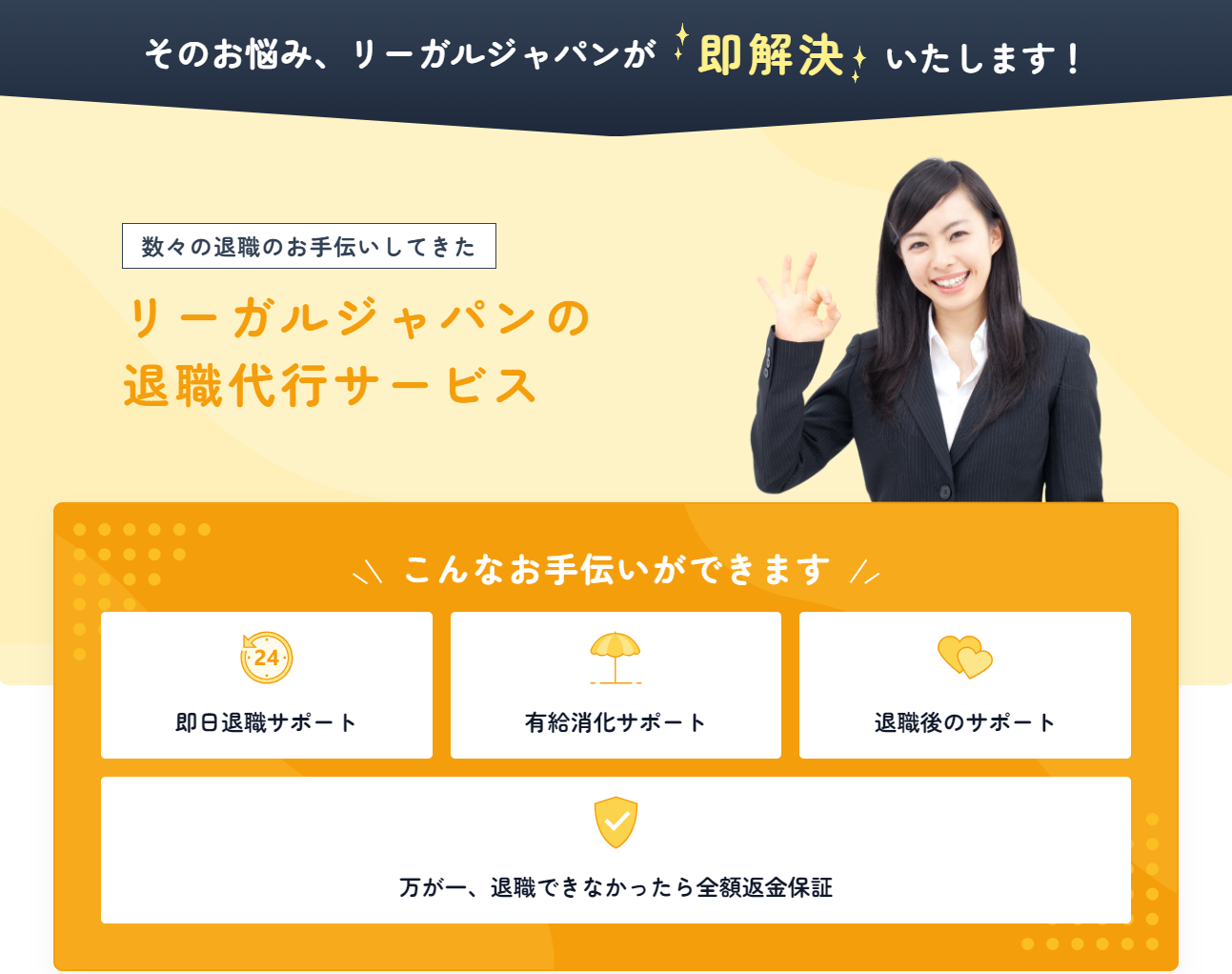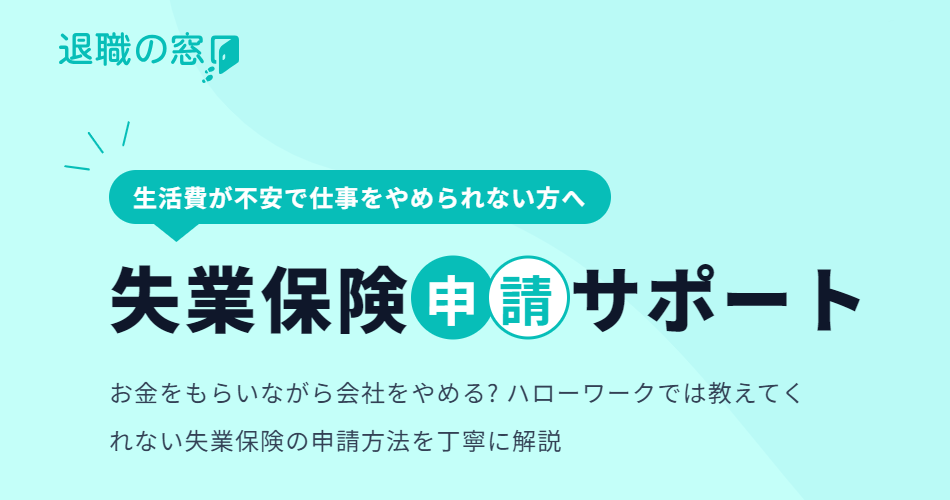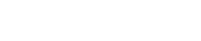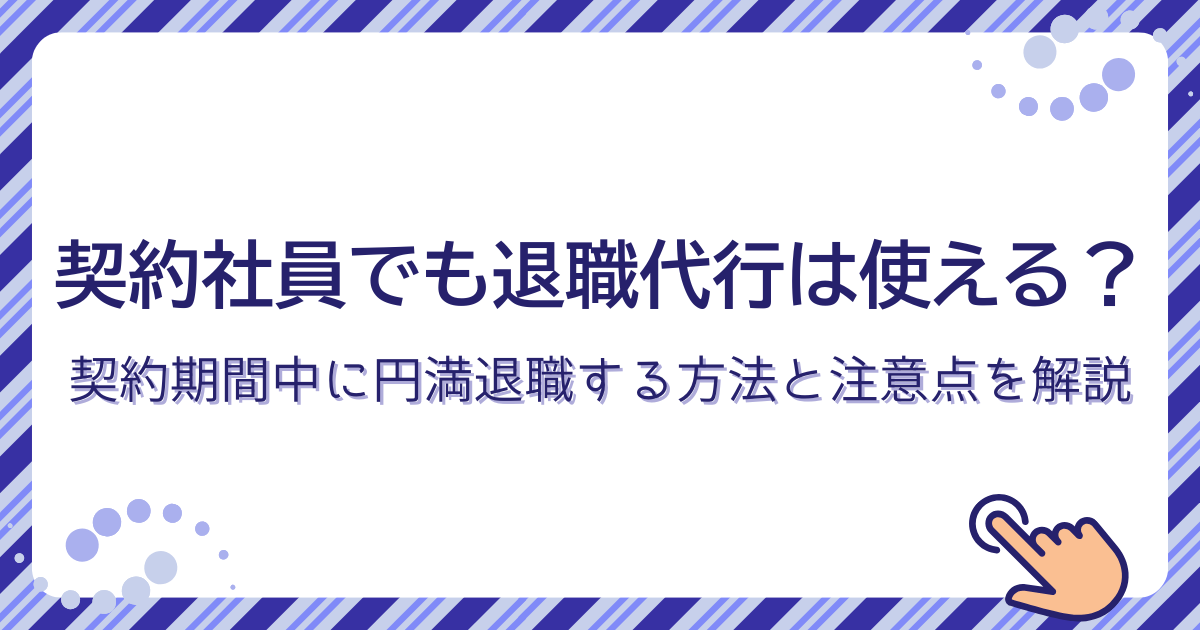「契約社員だけど契約期間中に辞めたい」「退職代行は利用できるのだろうか」と悩んでいる方もいるでしょう。
想像していたような職場環境や仕事内容ではなく、早めに辞めて次の勤務先を探したいと考えるときもあるのではないでしょうか。
契約社員は契約期間の途中であっても、条件によっては退職できる可能性があり、直接辞める意思を伝えられないときは退職代行を利用できます。
本記事では、契約期間中でも辞めたいと感じている契約社員の方に向けて、退職するための方法や注意点を解説します。
現在契約社員で退職したいと考えている方や、退職代行を利用する可能性がある方は、ぜひ参考にしてください。
契約社員は契約途中の退職が原則としてできない

原則として、契約社員は契約途中での退職は認められていません。
契約社員は勤務前に、期間を定めた契約を企業としているため、契約どおりに働く必要があります。
指示された仕事をしなかったり、無断で仕事を休んだりすると、契約内容によっては損害賠償を請求される可能性があります。
ただし、契約社員でも一定の条件を満たす場合は、契約期間中に退職できるため、どのようなケースで辞められるかを把握しておきましょう。
契約社員に契約期間中の退職が認められる主なケース

原則途中で辞められない契約社員の、退職が認められる主なケースは次のとおりです。
- 入社から1年以上が経過した場合
- 双方の合意がある場合
- 「やむを得ない理由」による場合
契約社員が契約期間中に辞められるケースを解説するため、辞めたいと考えている方は、当てはまっているか確認しましょう。
入社から1年以上が経過した場合
契約社員でも入社して1年以上勤務している場合は、いつでも退職を希望できます。
労働基準法第137条で定められている条文は、次のとおりです。
民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
引用元:労働基準法|e-Gov法令検索
上記の権利は、労働者を長期間不当に拘束するのを防ぐためのもので、会社側の合意や「やむを得ない理由」がなくても行使できます。
1年経過しているかわからない方は雇用契約書を確認するか、会社の担当部署に聞いてみるとよいでしょう。
双方の合意がある場合
契約期間中でも自身が辞めるのを会社や上司が認めてくれた場合は、契約社員でも退職が可能です。
会社側は契約社員の退職の申し出を拒否できますが、話し合いのうえで合意が得られれば、契約義務違反には当たりません。
双方の合意がある状態で退職すれば、無断欠勤で辞めた場合と比べて、損害賠償を請求されるリスクも少ないでしょう。
なぜ退職したいのか正当な理由があり、責任者と話し合える職場環境であれば、正直に伝えましょう。
「やむを得ない理由」による場合
何らかの「やむを得ない理由」がある場合は、契約期間中だとしても退職できます。
「やむを得ない理由」とは、自身の力ではどうすることもできず、働くことが客観的に困難になった状況を指します。
民法628条で定められている条文は、次のとおりです。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
引用元:民法|e-Gov法令検索
民法で定められている「やむを得ない理由」に関しては次章で解説するため、契約社員を辞めたいと考えている方は参考にしてください。
退職が認められる「やむを得ない理由」とは?

法的にも契約社員の退職が認められる主な「やむを得ない理由」は、次のとおりです。
- 自身の病気やケガ
- 家族の介護
- 職場環境の問題による場合
やむを得ない理由に関して詳しく解説します。
自身の病気やケガ
自身の病気やケガが原因で、働くことが難しくなった場合は、「やむを得ない理由」として退職が認められることがあります。
病気やケガで契約社員を退職する場合、医師が次の内容を記載した診断書が客観的な証明として有効です。
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 病名または傷病名 | 具体的な病名やケガの状態 |
| 療養期間 | 就労不能と判断される期間の目安 |
| 就労に関する医師の意見 | 業務継続の可否、必要な配慮事項 |
体調不良やケガで辞めたいと考える場合は、自身の健康や生活を最優先し、会社へ正直に状況を伝えることが大切です。
家族の介護
家族が病気や高齢などにより要介護状態となり、自身が介護をしなければならなくなった場合も、「やむを得ない理由」に該当します。
要介護状態とは、2週間以上常に介護が必要な状態を指し、判断基準は厚生労働省のサイトに明記してあるため、気になる方は参考にしてください。
他に介護を担える親族がいない、公的な介護サービスだけでは不十分といった状況だと、やむを得ない理由として認められやすくなります。
会社側から、家族介護の証明書などの書類を求められることが多いため、準備でき次第提出してください。
また、会社によっては契約社員の事情に応じて柔軟に対応する場合もあり、勤務時間の短縮や調整で介護と仕事を両立できるケースもあります。
職場環境の問題による場合
職場におけるパワハラやセクハラなど、会社や第三者に明らかな問題がある場合も、契約期間中の退職が認められる正当な理由となります。
また違法行為や契約どおりに給与が支払われない、契約した条件と勤務実態が異なる場合も、同様に退職可能です。
職場環境に何らかの問題がある場合、まずは社内の相談窓口や信頼できる上司などに相談するのも有効です。
ただし、ハラスメント行為に該当するのかは判断が難しいケースもあるため、必要に応じて弁護士に相談するのもよいでしょう。
契約社員が円満退職するために気をつけたい注意点

契約社員を退職すると決めた場合、できる限り円満に辞めたいとほとんどの方が考えるはずです。
会社を円満に退職したい方向けに注意点を解説するため、契約社員を辞めようと考えている方はぜひ参考にしてください。
就業規則に沿った退職手続きをおこなう
退職を決意したら、まず自身が働いている会社の就業規則を確認しましょう。
就業規則には、契約社員の退職に関するルールが記載されており、退職を申し出る期間が定められているケースがあります。
また、退職金や満了金に関するルールが定められている場合もあるため、契約満了まで勤務したほうがよければ退職しないのも選択肢の一つです。
会社とのトラブルを避け、円満に契約社員を辞めたいのであれば、就業規則に記載されているルールに則って退職を申し出ましょう。
無断欠勤や一方的な退職はしない
契約社員の方が会社を退職する際、絶対に避けなければならないのが、無断欠勤や一方的な退職です。
バックレや即日退職といった行動は、社会人としてのマナー違反であるだけでなく、さまざまなリスクも伴います。
起こり得るリスクの一例は、次のとおりです。
- 損害賠償請求
- 懲戒解雇処分
- 会社から本人や家族への連絡
- 転職への影響
話し合いが面倒、今すぐ契約社員を辞めたいなどの理由で無断欠勤や一方的な退職をすると、基本的によいことはありません。
まずは上司や責任者に退職を申し出て、スムーズに手続きや引き継ぎなどをおこなってください。
引き継ぎは丁寧におこなう
円満退職のためには、後任者や他の社員が困らないよう、責任を持って業務を引き継ぐことが非常に重要です。
引き継ぎは口頭での説明だけでなく、誰が見てもわかるような引き継ぎ書を作成するのが一般的です。
わかりやすい引き継ぎ書を作る際、重要な項目は次の表を参考にしてください。
| 項目 | 目的 |
|---|---|
| 業務の全体像 | 後任が仕事の流れを掴みやすくする |
| スケジュール | 優先順位をわかるようにする |
| 進捗状況 | 途中からの業務でも引き継げるようにする |
| データ・資料の保管場所 | 業務に必要な情報をわかるようにする |
| 関係各所の連絡先 | 必要な連絡先を把握させる |
| イレギュラー対応 | トラブル時に困らないようにする |
引き継ぎ書を作成したら、上司や責任者にチェックしてもらい、追加で記載したほうがよい情報があれば書き加えます。
完成した引き継ぎ書をもとに、後任者や関係する社員に口頭で説明し、最後まで誠意を持って丁寧に引き継いでください。
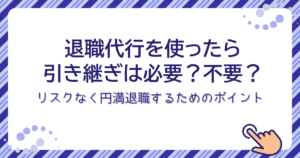
上司への退職意思の伝え方とタイミングに注意する
退職の意思の伝え方やタイミングは、円満退職において極めて重要です。
基本的に直属の上司や責任者へ退職の意思を伝えますが、建設的な話し合いになるよう努める必要があります。
また、会社の繁忙期に退職を申し出るのは社会人のマナー違反のため、意思を伝えるタイミングにも配慮しましょう。
会社の業務に余裕がある時期を選び、誠意を持って退職の意思を伝えれば、円満に契約社員を辞めやすくなります。
退職理由をストレートに言わない
給料が安い、職場環境に問題があるなどのネガティブな退職理由な場合、ストレートに上司や同僚に言わないようにしましょう。
会社の不満や人間関係の問題をストレートに伝えるのは角が立ちやすく、トラブルに発展する原因にもなりかねません。
上司に退職理由を伝える際は、できるだけ前向きな表現を心がけることが、円満な話し合いにつながります。
キャリアアップがしたい、専門性を高めたいなどポジティブな理由であれば、契約期間中の退職でも認められやすいでしょう。
退職するときは制度面にも注意することが大切
契約社員を辞める際、主に次の制度面に注意する必要があります。
- 有給の消化
- 健康保険や年金
- 退職後の雇用保険
制度面を意識しないと損をする可能性もあるため、契約社員を辞めたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
有給の消化は計画的におこなう
退職日までに残っている有給を消化する際は、会社に迷惑がかからないよう計画的におこなってください。
有給は労働者の権利ですが、いつでも消化してよいわけではなく、引き継ぎや業務に支障が出ないように配慮する必要があります。
まずは担当部署で残っている有給の日数を確認し、上司や責任者に有休消化について相談するとよいでしょう。
また、早めに引き継ぎを終わらせて退職日まで残っている有給を消化する形もとれるため、会社と話し合いながら計画を立てるのがスムーズです。
保険や年金などで必要な手続きを確認する
契約社員を退職する際は、健康保険や年金、雇用保険などの手続きが必要になります。
とくに健康保険や年金は、次の勤務先が決まっているか、次の就職まで空白期間があるかで手続きが異なるため、注意が必要です。
状況別の健康保険、年金の手続きの違いは次の表を参考にしてください。
| 手続きの種類 | 退職日の翌日に入社する場合 | 退職後に期間が空く場合 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 転職先が手続き | いずれかを選択・国民健康保険に加入・任意継続制度を利用・家族の扶養に入る |
| 年金 | 転職先が手続き | 国民年金に切り替え |
| 手続き・相談場所 | 入社する企業 | ・市区町村役場・健康保険組合・家族 |
上記のとおり退職後に期間が空く方は、それぞれの窓口で健康保険や年金の切り替え手続きをする必要があります。
手続きの方法がわからない方や疑問点がある場合は、各種窓口に問い合わせて相談するとよいでしょう。
退職後は失業保険(雇用保険)を申請する
契約社員を退職したあと、しばらく期間が空きそうな場合や次の勤務先を探す方は、失業保険(雇用保険)を申請しましょう。
地域を管轄するハローワークで手続きをすれば、退職後1か月半程度経過してから失業保険給付金を受けられます。
ただし失業保険をもらうには条件があり、給付額や期間などは人によって異なるため、事前によく調べておく必要があります。
退職後に失業保険の給付金を受け取りたいと考える方は、ハローワークのサイトや無料相談で、条件や必要書類などを確認してください。
契約社員でも退職代行は使える?

結論、契約社員でも退職代行サービスは利用できます。
自身が退職の意思を誠心誠意伝えていても、会社との関係が築けていなかったり、引き止めが強引だったりするケースもあるでしょう。
ただし、退職代行サービスは次のようなメリットもあれば、デメリットもあるため十分に検討する必要があります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・自身で退職を伝える必要がない ・精神的な負担を軽減できる ・即日退職できるケースもある ・会社と直接やり取りしなくてよい | ・費用がかかる ・円満退職にはなりにくい ・業者によってサービスが異なる ・会社から直接連絡がくる可能性 |
契約社員を辞めたい方が退職代行サービスを利用すれば、精神的な負担を軽くできる一方、自身が満足できる業者を選ぶ必要があります。
おすすめの退職代行サービスや、相性の良いサービスの選び方については下記記事も参考にしてください。
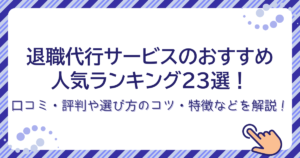
退職代行ならトリケシがおすすめの理由
退職代行を利用するなら、弁護士監修・サポート充実のトリケシがおすすめです。
相談実績が豊富なうえに、LINEで気軽に匿名相談もでき、契約社員を辞めたいと考えている方に向いています。
退職代行サービスのトリケシをおすすめできる理由を解説するため、自身で辞める意思を伝えにくい方はぜひチェックしてください。
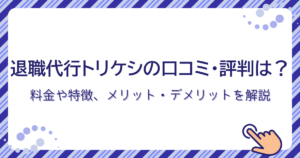
労働組合が運営・弁護士監修で安心
トリケシは弁護士が法的な観点から監修しており、労働組合が運営しているため、安心して利用できます。
労働組合が運営している退職代行であれば、有給消化をはじめとした会社との交渉ができ、損をせずに辞められる点が大きなメリットです。
民間企業が運営する退職代行に依頼すると、残っている有休の交渉ができないため、消化できないままの退職になる可能性があります。
弁護士監修・労働組合運営のトリケシであれば、すべての有給を消化してから辞めたいと考える契約社員の方でも、安心して退職できるでしょう。
24時間サポートで価格は業界最安レベル
トリケシは24時間LINEでの相談に対応しているため、最短即日での退職も可能です。
退職後も必要書類の受け取り、給与未払いなどのトラブルへのサポートも充実しており、無料で転職の相談もできます。
またサービス価格は、退職代行業界最安レベルの19,800円(税込)で、追加費用は一切かかりません。
そのため、できる限りコストは抑えたい、はじめての退職代行で不安と考える方におすすめしたい退職代行サービスです。
全額返金保証付き・後払いもOK!
トリケシは、全額返金保障付きです。万が一申し込み後1か月以内に退職できなかった場合は支払い金が戻ってくるため、お金が無駄になることはありません。
また退職後の後払いも可能で、辞めるのが確定してから支払いたいと考える方でも安心して利用可能です。
支払うタイミングは自由に選べて金銭面での安心も大きいため、契約社員を辞めたいと考えている方は、気軽に相談してみましょう。
退職が不安なときの相談窓口
契約社員として退職を考える際、法的なことや手続き、次の仕事のことなどさまざまな不安や疑問が出てくるでしょう。
退職が不安なときに相談できる無料窓口は、次のとおりです。
契約社員を辞めたいけれど、手続きや今後の仕事が不安な場合の相談窓口を紹介するため、ぜひ参考にしてください。
ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)は、国が運営する雇用に関する総合的なサービス機関のため、さまざまな相談が無料でできます。
失業保険の相談や手続きをはじめ、再就職に向けた求人情報の検索や書類作成・面接対策などのサポートも受けられる窓口です。
また、再就職に役立つイベントやオンラインセミナーなども実施しており、退職検討時や辞めたあとが不安な方でも安心できます。
契約社員退職後の生活設計や次の仕事探しに不安がある方は、まずハローワークに相談してみましょう。
労働基準監督署
労働基準監督署は、労働基準法などの法令に基づいて、企業が法律を守っているかを監督する国の機関です。
会社が賃金を支払ってくれない、職場でハラスメントを受けているなど、仕事に関する問題やトラブルが発生した場合に、無料で相談できます。
たとえば、違法な長時間労働を強いられる際は、法律に基づいた具体的な対処法や解決策についてアドバイスをもらえるでしょう。
労働基準監督署の他にも総合労働相談コーナーや、電話での相談も受け付けているため、仕事に関する悩みがあれば相談してください。
契約社員の退職に関するよくある質問

契約社員の退職に関して、よくある質問と回答をまとめています。
契約期間中でも契約社員を辞めたいと考えている方や、失業保険などが気になる方は、ぜひ参考にしてください。
契約期間中に退職すると損害賠償を請求されますか?
「やむを得ない理由」がある場合や、会社との合意に基づいて退職する場合などであれば、損害賠償請求される可能性は極めて低いでしょう。
ただし、会社に相談なく一方的に辞めるなど、無責任な辞め方をして会社に損害を与えた場合は、請求されるリスクがあります。
ネガティブな理由で契約社員を辞めたい場合でも、契約内容や就業規則に則って退職するのをおすすめします。
契約満了でそのまま辞める場合はいつ伝えればいいですか?
契約期間満了をもって契約社員を辞める場合、就業規則で定められている退職の申し出期間を参考にするとよいでしょう。
また、契約書に退職の意思を伝える期日が定められていることもあるため、事前に確認しておく必要があります。
一般的には1〜2か月前に辞める意思を伝えるケースが多いものの、早いに越したことはありません。
退職届はどうやって提出すればいいですか?
退職届は、まず直属の上司に口頭で退職の意思を伝え、退職日などが正式に決定した後に提出するのが一般的です。
また退職手続きの一環として、手渡しで提出するのが基本ですが、会社によっては書式や提出方法が指定されているケースもあるため確認してください。
上司に受け取ってもらえない場合は、人事部に提出する旨を報告したうえで人事担当者に退職届を提出します。
自己都合で退職しても失業保険はすぐもらえますか?
自己都合退職の場合、原則として待期期間7日間に加え、1か月の給付制限期間があります。
そのため、契約社員を辞めてもすぐには失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できません。
ただし、病気や家族の介護、ハラスメントなどが理由の正当な理由のある自己都合退職と認められれば、給付制限期間なしで受給できる場合があります。
失業保険をすぐにもらいたいうえに、退職に正当な理由がある方は、ハローワークでの相談がおすすめです。
まとめ
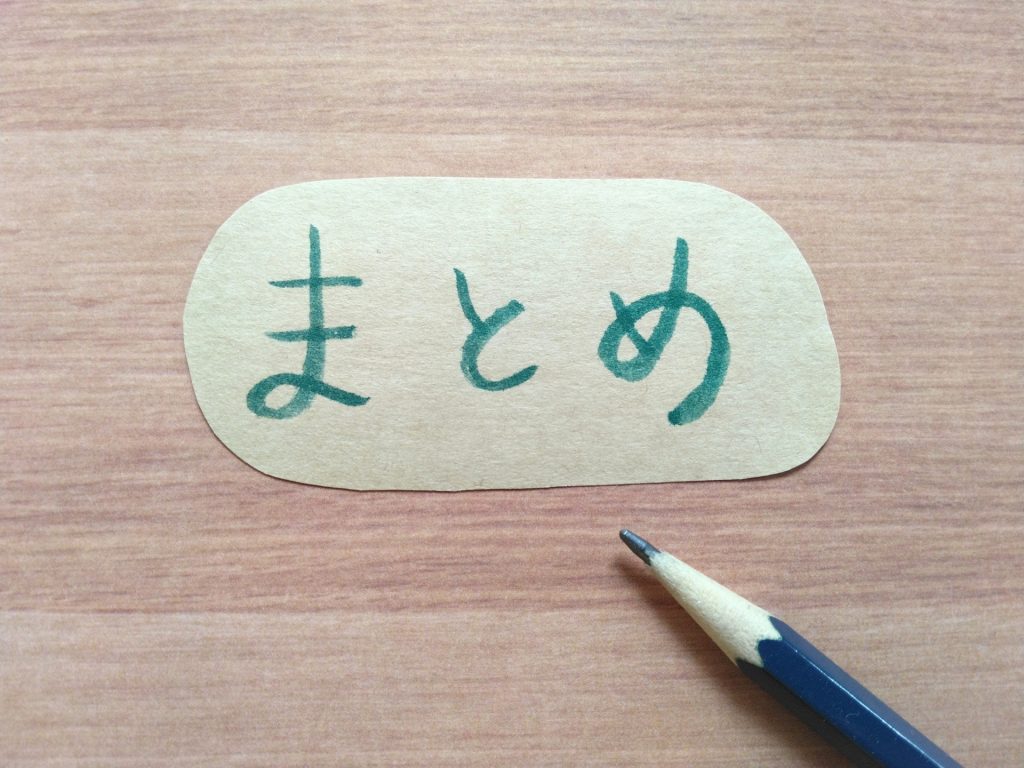
契約社員を辞めたい方向けに、契約期間中でも退職が認められるケースや円満に辞めるための注意点などを解説しました。
原則契約期間中に辞められない契約社員でも、次のような場合は退職できます。
- 入社から1年以上が経過している
- 双方の合意がある
- 「やむを得ない理由」がある
上記のような場合は契約社員でも退職できるため、就業規則や契約書に則って手続きを進められます。
契約社員を辞めたいと考えている方は、本記事の内容を参考に退職の意思を伝え、手続きなどもスムーズにおこなってください。
仮に会社とやり取りしたくない、引き止めが強引などの場合は、退職代行サービスのトリケシの無料相談を活用しましょう。